|
最新ニュース
<<2025年第4四半期>>
日本IBMが材料研究DXの統合支援サービス、AI/データ化学活用
2025.12.18−日本IBMは16日、材料開発に特化した研究DX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する統合サービス「IBM Material
DX」を日本向けに提供開始すると発表した。材料科学に長年の蓄積があるIBMリサーチの情報資産と、コンサルティング、最新ITテクノロジーを組み合わせて、データ駆動型の材料研究手法を顧客内に根づかせるために、伴走的で全方位的なサービスを提供する。とくに、人工知能(AI)やデータ科学の活用を主眼としており、研究開発の期間とコストを10分の1以下に削減することが目標になるという。
ノーザンサイエンスが中国XtalPiと販売提携、結晶学研究を統合支援
2025.12.12−ノーザンサイエンスコンサルティング(NSC)は、医薬品開発向けの人工知能(AI)やロボティクス/自動化技術を持つ中国のXtalPi社と日本市場に対する代理店契約を結んだ。まずは、製剤研究に直結する結晶構造予測・結晶多形予測などを行う統合サービス「XtalGazer」の紹介から日本市場への展開を開始する。原薬などの化合物を実際に試験し、AIや計算化学(量子力学・分子力学)を組み合わせて、医薬・精密化学・化粧品などの結晶学研究を受託あるいは統合的に支援する。「NSCとのパートナーシップにより、3〜5年で日本市場を3〜5倍に拡大できる」(トラビス・ヒュー上級副社長)と期待している。
-----------------
富士通がニューラルネットワーク力場、大規模・長時間シミュレーション
2025.09.08−富士通は、第一原理計算結果を機械学習して、高精度な材料シミュレーションを超高速に実行するニューラルネットワーク力場(NNP)作成ツール「GeNNIP4MD」を開発した。訓練データセットの作成や、機械学習モデルに対する訓練と結果の評価、性能が十分でない場合のデータ拡張など、繁雑な作業手続きやそのための専門的なノウハウが必要だが、このツールを利用すれば自動的にNNPを作成することが可能。アクティブラーニングなど精度を高めるための同社独自の工夫も盛り込んでおり、個別ユーザーとのPoC(概念実証)/PoV(価値実証)プロジェクトを通して実用化を図っている。
モルシスが英ハンソンウェイドの「Beacon」、モダリティごとに専門情報
2025.08.27−モルシスは、英ハンソウェイドが提供している医薬品開発のための意思決定支援ツール「Beacon」の国内販売権を取得し、販売を開始した。医薬品の詳細データから臨床試験情報、市場動向分析まで、包括的に網羅された情報を可視化することで、迅速で正確な競合情報の把握と、的確で素早い意思決定を行うことができる。情報は毎日アップデートされており、自力では集めきれない情報が簡単に得られるということで、欧米の大手製薬企業のほとんどが利用中だとされる。正式に日本で展開することとなり、大きな反響が期待される。
米CASがAIでSciFinderを機能強化、科学スマートAIを搭載
2025.08.23−米ケミカル・アブストラクツ・サービス(CAS)は4日、科学情報の検索と洞察のための統合ソリューションである「CAS SciFinder」に新しい人工知能(AI)機能を順次搭載していくと発表した。“科学スマートAI”(Science-smart AI)と呼ぶアプローチを採用しており、CASが長年蓄積してきた高品質で構造化された科学データ(CAS Content Collection)をベースに、科学者による検証を経たAIモデルを組み合わせることで、信頼性の高い科学的回答を提供できるようにしている。構造検索、反応検索、知的財産(IP)検索の各場面で利用できるAI機能が用意されており、今後2カ月間にわたって順次提供開始される。
-----------------
ダッソー・システムズのビオ副社長会見、バーチャルで治療効果など実証
2025.06.28−ダッソー・システムズは27日、クレア・ビオ(Claire Biot)ライフサイエンス&ヘルスケア業界担当副社長による記者説明会を開催、同事業に関連する最近のプロジェクト事例などを紹介した。中枢神経系治療薬の脳内への分布シミュレーション、インシリコ臨床試験への取り組み、バーチャル心臓を使った治療−などを進めている。日本の製薬メーカーや医療機器メーカー、医療従事者や患者などからのさまざまなニーズをとらえ、「バーチャルツイン技術で貢献していきたい」(ビオ副社長)としている。
Asedaサイエンスが日本市場に意欲、毒性等を判定して意思決定支援
2025.06.04−スイスに本社を置くAsedaサイエンス(ブラッド・カルヴィンCEO、Brad Calvin)が日本市場に意欲を示している。事務所の開設などはまだだが、日本人担当者を置き、営業・マーケティング活動を開始した。化学物質の毒性や体内動態を動物実験を使わずに評価するサービスおよび研究用統合ソフトを、「3RnD」の名称で欧米でも提供し始めたところ。独自に蓄積した高品質なデータをもとに、人工知能(AI)を利用して研究上の意思決定支援を行うことができ、医薬・農薬、化学品、化粧品、食品などの研究開発に活用することが可能。医薬品開発受託機関(CRO)としてもビジネス展開している。
-----------------
米OpenEye:アンソニー・ニコルズCorporate VPインタビュー
2024.12.04−米国のOpenEye, Cadence Molecular Sciencesは、世界中の顧客を対象に創薬の加速を目的としたソリューションを提供している。2022年に米国を拠点とする電子設計(EDA)ソフトウェア企業であるCadence
Design Systemsグループの一員となってからも、同社は創薬プロセスを迅速化する革新的な物理学ベース、科学主導のAIソリューションの提供に力を入れてきた。ライフサイエンス市場に重点を置くOpenEyeは、製薬会社、バイオテクノロジー企業、農業部門など多様な顧客にサービスを提供している。Corporate
VP & GM Research & Developmentのアンソニー・ニコルズ氏(Anthony Nicholls)に、製品戦略や日本での事業展開などについて聞いた。
材料研究分野でLLMに注目、QunaSysがコンソーシアムでアンケート
2024.10.31−化学・材料研究において、生成AI(人工知能)のコア技術である大規模言語モデル(LLM)への関心が高まっている。量子コンピューター関連のスタートアップであるQunaSysが主催しているコンソーシアム「材料開発LLM勉強会」で、参加者へのアンケートをとった結果、実態や期待のほどが明らかになった。今年9月に終了した第1期活動のまとめでは、材料開発におけるLLM活用が、「1〜3年以内にブレークスルーを起こすユースケースが発見され、爆発的に使用が広がる」と答えた割合が41.2%、「5年後には社内で定着し、材料開発の革新が進む」が35.3%となるなど、参加者は大きな手応えを感じたようだ。
-----------------
QunaSysが材料開発向けLLMモデル実用化へ、コンソーシアム方式で
2024.03.28−量子コンピューター関連のソフトウエアベンダーであるQunaSysは、材料開発に適した大規模言語モデル(LLM)の実用化を目指し、研究と活用を目的としたコンソーシアム「材料開発LLM勉強会」を旗揚げした。非競争領域における材料メーカー同士の協働を意図したもので、参加費用は1社当たり100万円から。まずはメンバーの参加を募り、6月から本格的に活動していく。
AWSが製薬業向け事業戦略を強化、生成AIの利用進展
2024.02.21−アマゾンウェブサービスジャパン(AWSジャパン)はこのほど、昨年行われた年次イベント「AWS re:Invent 2023」における製薬業界向けセッションをまとめた記者説明会を開催した。製薬業界の顧客トレンドとして、(1)生成AIの利用ステージが進展し、検討段階から業務実装フェーズに入っている、(2)ゲノム/臨床データ量の爆発に対してクラウドの活用が進んでいる、(3)製薬バリューチェーンのあらゆる段階でクラウド活用が加速している−などの傾向がみられたという。AWSではすでにこれらに対応した取り組みやサービス提供を進めており、今後は日本の製薬業界に対する投資を拡大させる方針だとした。
-----------------
分子機能研究所が大学との共同研究推進、がん治療薬開発など
2023.11.07−分子機能研究所は、独自の構造ベース創薬(SBDD)技術を利用し、大学との共同研究で成果をあげている。研究プロジェクトのうち、インシリコ創薬を実施するパートを担当しているもので、がん治療薬の開発をターゲットに、大阪大学産業科学研究所および京都府立医科大学創薬センターと、それぞれ共同研究を開始している。これらアカデミックでの実績をテコに、民間向けに提供している「MFDDインシリコ創薬受託研究サービス」をさらに推進していく考えだ。
-----------------
米CASとポーランドのMolecule.oneがAI応用で戦略的提携
2023.08.18−ケミカルアブストラクツサービス(CAS)は11日、低分子創薬の生産性を向上させるため、ポーランドのワルシャワに本社を置くMolecule.one
と戦略的提携を結んだと発表した。CASが蓄積している世界最大級の化合物情報を利用して学習した生成AIを使って、新しい低分子薬候補化合物の合成のしやすさなどを評価したり、最も効率的な合成経路を的確に探索したりできるようにする。今週、サンフランシスコで開催された米国化学会「ACS
Fall 2023」で公開された。創薬研究の確実性と効率性が高まると期待される。
アイデミーがSaaS型MIサービス「Lab Bank」を提供開始、データ活用基盤
2023.08.01−アイデミー(本社・東京都千代田区、石川聡彦社長兼CEO)は7月31日、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)のためのデータ活用プラットフォーム「Lab
Bank」を提供開始すると発表した。SaaS(サービスとしてのソフトウエア)で提供される新サービスで、研究データの一元管理、機械学習モデルに基づく物性予測、実験結果の予測を行い、研究開発にともなう実験回数や時間の削減を可能にする。1年間単位の契約となり、蓄積したデータは社内システム等で活用することもできる。
-----------------
Revvity Signals Software(レビティ)が始動、旧パーキンエルマー
2023.06.08−レビティシグナルズソフトウェアが始動した。パーキンエルマーのインフォマティクス事業部の名称が変更したもの。新しい社名およびブランド名である「REVVITY」は、“変革する”(revolutionize)とラテン語で“生命”(vita)を意味する言葉を組み合わせたもので、「ライフサイエンスに革命を起こす企業」になる意識を込めたものだという。ニューヨーク証券取引所(NYSE)のティッカーシンボルも、5月16日にそれまでのPKIからRVTYに変わった。将来性の高い部門に重点を置き、残りを売却するという変革が完了したことになる。
富士通がペプチド創薬の研究プロセス管理プラットフォーム、DMTAを加速
2023.05.19−富士通は18日、ペプチド創薬の研究プロセスを管理するプラットフォーム「Biodrug Design Accelerrator」(バイオドラッグデザインアクセラレーター)を製品化し、販売開始したと発表した。今年度の第3四半期からはグローバルにも順次展開していく。ペプチド医薬品の候補として抽出された数千種類の化合物を、数十種類まで絞り込む過程において、研究プロセスの可視化やデータの一元管理、研究者間のコラボレーションを可能にすることにより、DMTA(設計・合成・評価・分析)サイクルを加速させることを狙う。研究対象として、ペプチドだけでなく核酸医薬品や抗体医薬品にも対応できるほか、将来的には人工知能(AI)やシミュレーション技術の統合も図っていく予定。
東大・溝口教授らがAIで全電子構造を決定する新手法、スペクトルで予測
2023.05.18−東京大学生産技術研究所の溝口照康教授、東京大学大学院工学系研究科のチェン・ポーエン大学院生、東京大学生産技術研究所の柴田基洋助教、防衛大学の萩田克実講師、東北大学の宮田智衆助教の研究グループは、人工知能(AI)によってスペクトル情報からその原子の全電子構造を決定できる手法を開発した。スペクトルと全電子構造をそれぞれ約11万7,000個ずつ計算し、その相関をニューラルネットワークに学習させたもの。学習で用いた分子よりも大きい100原子程度の分子にも適用できる予測モデルも構築した。高い空間分解能を有する内殻電子励起スペクトルを用いているため、原子一つ一つに対応した「原子レベル全電子構造計測」の実現につながると期待されるという。
シンガポールのPolymerizeが日本法人設立、MIプラットフォームサービス
2023.05.17−マテリアルズ・インフォマティクス(MI)のプラットフォームサービスを提供するシンガポールのPolymerize(Kunal
Sandeep CEO)は、日本法人を設立し、5月1日から営業活動を開始した。きょう17日からインテックス大阪で開催される「高機能素材Week」に出展し、国内で初お披露目を行う。
PFCCがMIクラウドサービス「Matlantis」を米国市場で展開、72元素に対応
2023.05.01−Preferred Computational Chemistry(PFCC)は4月28日、汎用原子レベルシミュレーター「Matlantis」(マトランティス)を米国市場で提供開始したと発表した。これはマテリアルズ・インフォマティクス(MI)研究を実行するためのクラウドサービスで、国内では2021年7月にリリースされ、すでに50以上の企業・研究機関での利用実績がある。世界のMI研究の中心地であるともいえる米国での反響が注目される。
-----------------
富士通とAtmoniaがアンモニア合成触媒探索、AIで量子化学計算高速化
2023.02.22−富士通とアイスランドのベンチャー企業 Atmonia(アトモニア)社は21日、アンモニアをクリーン合成するための触媒探索の共同研究において、量子化学シミュレーション高速化技術を開発、これと富士通の人工知能(AI)技術を組み合わせることで、触媒剤両候補を探索する期間を従来の半分以下に削減することに成功したと発表した。HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)計算結果をもとに、AIによる機械学習で触媒候補を絞り込むシミュレーションモデルを確立したもの。常温常圧で水と空気と電気からアンモニアを効率良く合成するための触媒発見につながると期待される。
CTCと三重県工業研究所が陶磁器製造でMIの実証実験、原料配合など
2023.01.13−伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は、三重県工業研究所との間で、陶磁器製造に関する人工知能(AI)を応用したマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の実証実験を推進。耐熱性や吸水率など陶磁器の機能性を向上させるための最適な原料配合や焼成条件を探索するAIモデルの開発を目指している。
日立ハイテクソリューションズと慶應義塾大学がMI利用し創薬研究
2023.01.12−日立ハイテクソリューションズは11日、慶應義塾大学薬学部とマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の活用で共同研究を開始すると発表した。日立ハイテクソリューションズが製品化しているMIツール「Chemicals Informatics」(CI)を、いわゆるAI創薬分野に応用する取り組みであり、低分子薬をターゲットにしていく。
...............................................
一般ITニュース CCSニュース CCSニュース アーカイブ アーカイブ
<<2025年第3四半期>>
ダッソー・システムズが航空宇宙分野の戦略強化、国内向けイベント
2025.09.18−ダッソー・システムズは10日、大阪・関西万博のフランスパビリオン館内の施設を利用し、国内の航空宇宙関係者を招いて「Space
Event(スペースイベント)」を開催した。同社がフランスパビリオンのシルバーパートナーであることから実現したもよう。イベントに合わせて来日したデイヴィッド・ジグラー(David
Ziegler)航空宇宙・防衛バイスプレジデントに、航空宇宙産業の動向や日本での事業戦略などを聞いた。
ダッソー・システムズが関西で初の年次イベント、3Dユニバースへ発展
2025.09.16−ダッソー・システムズは、9日と10日の両日、大阪市北区のANAクラウンプラザホテル大阪で年次ベント「3DEXPERIENCE Conference Japan 2025」を開催した。関西で開くのは初めて。先進ユーザーの活用事例が多く発表されたほか、幅広いソリューションの各ブランドにおける人工知能(AI)戦略などが紹介された。同社が提唱している第7世代の“3D UNIV+RSES”(3Dユニバース)への発展が強調されたイベントとなった。
富士通が医療機関の業務向け特化型AIエージェント開発へ
2025.08.29−富士通は27日、医療機関の経営効率化と安定的な医療の提供に向け、ヘルスケアに特化したAIエージェントの開発を進めると発表した。患者と対面し、受け付けや問診、診療科への振り分けなどを行う専門特化したAIエージェントを、全体をオーケストレーションするAIエージェントが束ねる構成で、NVIDIAを開発パートナーとして連携する。年内には、先端的な医療機関と有効性の検証を行うプロジェクト体制を組み、具体的なエージョンと開発を進めるとしている。
「富岳NEXT」開発プロジェクトが本格始動。加速部GPUにNVIDIA参加
2025.08.23−理化学研究所は22日、次世代フラッグシップスーパーコンピューター「富岳NEXT」(開発コード名)の開発体制を確立・始動させた。すでに、CPUおよび全体システム化の共同開発先として選定されている富士通に続き、GPUによる計算加速部を米NVIDIAが担うことが決まり、国際連携によるプロジェクトが本格的に始動した。今年度に、3者による基本設計を行い、来年度から詳細設計に入る。稼働が開始される2030年ごろに、世界最高のAIスーパーコンピューターであることを目標に開発され、人類共通の社会課題を解決するような成果を示すことで、同機を構成する諸技術を世界に普及させることを目指すという。
-----------------
ロックウェル・オートメーションが製薬向けMES、デジタルプラント成熟化
2024.11.01−ロックウェル・オートメーション(矢田智巳社長)は、日本市場に対して製薬業向けの製造実行システム(MES)の提案に力を入れる。製造プロセスを標準化・自動化して、品質の安定やコスト削減に効果をもたらすもので、製薬業におけるデジタルプラント成熟度モデル(DPMM)の適用に道を付けることが可能。国内で大手製薬企業と導入プロジェクトが進行しており、来年早々にはセミナー開催などを計画し、本格的な営業活動を展開していくことにしている。
-----------------
NTTの秘密計算技術がISO国際標準に採択、統計分析やAIなど高速処理
2024.03.23−NTTは21日、データを暗号化したまま元に戻さずに処理をする“秘密計算技術”について、同社が開発した技術が国際標準化機構(ISO)に採用、採択されたと発表した。秘密計算技術のうち、“秘密分散”と呼ばれる方式を規定したもの。今回、具体的なアルゴリズムが定められたことにより、実際のISO標準に基づく秘密計算が実装できるようになった。今後、すでにいくつかの実績がある実証実験をさらに拡大させるほか、さらに研究開発を進め、社会実装の推進に取り組んでいくとしている。
-----------------
B2Bマーケティングで日本企業を強く、シンフォニーマーケがイベント
2023.08.22−「日本企業に欠けている機能はマーケティング。ここを改善すれば日本企業は強くなる」。8月上旬にシンフォニーマーケティング(庭山一郎代表取締役)が都内で開催したカンファレンス「IGC
Harmonics 2023」では、B2Bマーケティング従事者(マーケター)がすぐに実践して活用できる学びと、マーケター同士が交流し情報交換ができる刺激の場として有意義なプログラムが実施された。欧米では、企業内におけるマーケターの地位が高く、CMO(最高マーケティング責任者)へのキャリアアップ、さらにはそこからCEO(最高経営責任者)へと上り詰める例もあるという。「マーケターが影響力を持つことでまわりが活性化される」とのことで、マーケターのスキル向上を図ることが戦略上の目標になることが強調された。
ENEOSとPFNがAIによる自動最適運転を実プラントに常時適用
2023.08.01−ENEOSとPreferred Networks(PFN)は7月31日、ENEOS川崎製油所のブタジエン抽出装置に対して、人工知能(AI)による自動運転システムを常時適用開始したと発表した。大規模かつ複雑であり、長年の経験に基づいた運転ノウハウが求められる同プラントにおいて、手動操作を超える経済的で高効率な運転を達成したとしている。
-----------------
横河ソリューションサービスとNTTコミュニケーションズがプラント自動運転
2023.01.31−横河ソリューションサービスとNTTコミュニケーションズは1月30日、運転員の操作を学習した人工知能(AI)によって化学プラントの自動運転を実現する「オートパイロット」の提供を2月から開始すると発表した。事前に、JNC石油化学の市原製造所に導入し検証したところ、従来技術では制御が難しかった工程の自動運転に成功するとともに、運転員による手動での操作を上回る精度を示したという。
-----------------
...............................................
|
![]()
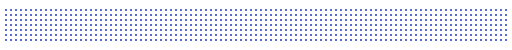
![]()